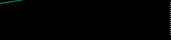だいちゃん Diary

ロボット?
サングラスのネジがゆるみ、特殊なネジなので新浦安駅のアトレにあるメガネ店へ。修理後、そこで買ったメガネではないので料金を聞くと「結構です」と言われた。予期していたことで多少のお金を店頭に設置してあった募金箱に入れた。
アトレの駐車場にいれたので駐車代金を免れるためには、千円の買い物が必要。目に止まったのがユニクロ。靴下が不足気味だったので売り場に直行すると4足990円の表示。靴下を選んだ後レジにて、無理を承知で駐車券にスタンプをもらえと質問。あっさりと断られ、買い物はキャンセル。成城石井で1970円のブラックボトルを購入。
ついでにブライトンホテルへ、4日前に買ったラスクが油の質か悪く余りにも不味かったので、ほとんど手付かずの商品を返しに。レシートの有無を聞かれ、無いと答えると返金は出来ない言われた。返金が目的ではない、二度とこんな商品を並べてほしくないだけ。電話番号だけ聞かれたので書き残して帰る。一時間後上席らしき人から「貴重なご意見有難う」と電話があり、それで終わった。私として「やはり不味いですね」に類する一言が欲しかったが、立場上言えないのも解る気がする。
メガネ屋は例に適さないが、店のマニュアルを優先しすぎて相手の気持ちは二の次、人間味が少ない気がする。
機械的な仕事なら、働く人が面白くないかも。
目的が変る ②
ソニーのミラーレスカメラ(sony nexf3)、埋め込み式のストロボがちょっとした衝撃でも飛び出すようになりメーカー保障で修理にだす。修理を依頼し10日しても連絡がないので催促の電話と入れると、この故障は保証の対象外とのこと。一度落としたこともありボディにはキズもあり、それが起因しているとの説明。落としたことは事実だか、ストロボ収納時に引っかかり部分が弱くそれが原因だと思っていたのでクレームを入れた。原因にしては平行線と辿り、お客様窓口のH氏の強気で誠意のない応対に不満も感じつつ、再度見解を出して欲しいと依頼した。電話を切った後「何ためにカメラと修理に出したか」その目的を自分自身に問うてみた。気に入ったカメラを長く使うことが目的であったはずの修理、このままではソニーのサービスセンターへの不誠実さへのクレームが目的になってしまいそうだ。お客様対応のセクションではこんなやり取りが頻繁に行われておりそれはソニーの問題で、自分として関わりたくない世界に思えてきた。結局修理しないで戻してもらうことにした。
目的が摩り替わるはいくつもある。買い物も同様でショッピングポイントを気にして購入する人も多いが、私自身は割引をポイントとして貯めることには関心がない。快適な生活を維持するための買い物が、ポイントを貯める目的に置き換えたくないから。
新チャーター便 6月1日よりスタート
6月1日より、関東地区のチャーター料金を大幅に値下げしたサービスを開始します。
長尺(長い物)やパレット物の混載(積み合せ)を運営しております20台の車輌が関東地区を広範囲に走っており、その車輌を活用してチャーター便の運行も合せて実施する運びになりました。回送距離も少ない為運賃も低価格で提供でき、タクシー感覚の料金でご利用いただけます。是非ご利用下さい。
目的が変る
ボランティア活動で老人の家庭に入った時、感謝の気持ちからお礼に一万円を貰ったとする。この様なことが度々続くと、そこに行くことの目的が奉仕からお金を貰うことにいつの間にかすり替わる。職探しにハローワークに、そこで進められるのが職業訓練。その訓練を受講すると手当てがでる、いつの間ににか職探しから手当てをもらうことが目的になる。怖いことである。会社で過去に人材育成の助成金を数年間もらったことがある。その時も同様な事が起きた。社員の人材育成のカリキュラムが、いつの間にか助成金を効率的にもらうことが目的になり、人材教育が二の次になっていた。
2000年にお客様と鉄鋼物流の合理化の可能性に意気投合して、メタル便という会社を起こした。新規事業でリスクも大きい中、サービス提供に必死になってきた。継続する内にお客様が増えて仕事が順調に回り始めると、維持拡大や収益が目的にすり変る可能性もある。メタル便は「鋼材流通のプラットホーム」作りを目的として、共同配送によりコスト削減を具体化する仕組みだ。その目的に共感して多くの協力者があってここまで来れた。初心忘れるべからず。目的貫徹の難しさを痛感するこの頃だ。
北海道で共同配送の打合せ
北海道の丸和運輸機工様の事務所で、積み合せ運送をテーマにミーティング。
当社は建築資材・鋼材・長尺物・パレット物が扱い商品だが、北海道でアイスクリームの共配を提供するH社の社長や、チョコレート等の共配や3PLを全国規模で提供するK社の社長にも加わってもらい共同配送について異なる視点で意見が交わされた。共同配送にこだわらずリードタイムやチャンネルを縮めることの重要性も再認識した。
すみれのラーメン
ラーメンにそれほど詳しくなくても、北海道の「すみれ」の名は知っている。宿泊ホテルのフロントに場所を教えてもらい初チャレンジ。普段は行列の店だが、日曜日とあってすぐ席に座れた。半分位は観光客で並んで座っていて、これから出てくるラーメンへの期待やワクワク感が伝わってくる。
ここからが小さな感動の連続
入り口に食券自販機が置かれており、自販機がわからず着席して注文するお客に店員は注意することなく自販機で食券を買ってあげていた。サーブの時はどのお客様にも必ず「熱いのでご注意下さい」と「ごゆっくりどうぞ」と言っていた。カウンターには冷水の入った小さなヤカンが置かれていたが、お客様の退席の度にヤカンをチェンジして次のお客様にそなえていた。そしてスープをすべて食すると器の底に「感謝」の文字。実際のサービスと「感謝」の文字が一致しているからその文字を見たときより感動した。繁盛店=無愛想と勝手に決めていたが、一つ一つのキメ細かい接客にファンになってしまった。
基本をしっかりやり継続しているからお客様から変らぬ支持を得ているのだろう。勿論食べた味噌ラーメンは絶品だった。「熱いのでご注意下さい」の言葉を聞き流して、がっついてスープをれんげで飲んだので、舌が軽いやけど状態になり半日違和感が残った。スープが冷めない為に薄く油の膜が張られているらしい。
働く人の汗に報いる
2011年春に内容証明が届いた。在籍しているドライバーA君からで、過去2年間で残業未払いが100万円あり即刻支払えという内容だった。A君は歩合制と残業を併用している給料体系で、まさかと思い過去2年間のタイムカードと売上と賃金台帳を付け合せたら確かに会社に否があり24万円の未払いが判明した。その主旨を伝えると、A君は不服として労働基準監督署に駆け込んだ。争点は休憩時間になった。結局A君は労働基準監督暑の認めた金額にも納得せず「あっせん」、でも歩み寄れず裁判になった。双方に社会労務士や弁護士がつき相当額の費用も発生した。一年以上かけ判決を得ることなく和解で幕を閉じた。
振り返ると経験したことがない「あっせん」や裁判に、運転手の生活を守る為にしてきたビジネスでまさかの訴訟、気の重い一年間だった。幸いしたのは給料体系や就業規則を全て見直しができたこと。でも就業規則の条項は以前の倍以上になった。その間、心のよりどころとなったのは「働く人の汗に報いる」という経営理念の一項目だった。
会社を信用して一生懸命に働いてくれる運転手に公平に報いたい、安心して働ける職場を作りたいとの想いを深くした出来事だった。
鈴木木材店
鈴木木材店と言う顧客は存在しない。
木材関係全般は鈴木、貿易関係は古賀が担当しており、それを称して鈴木木材店、古賀貿易と称している。その様に表現するのはもう一つ理由があり、最近この関係の仕事が急激に増えているからだ。木材や貿易はお客様からの口コミが多い。特に長尺物やパレット物の混載に関しては「あの会社なら積み合せで運ぶよ」と紹介していただける。
お客様から受注する時、扱い商品に熟知したスタッフがお客様の窓口になる。当社では鋼材や紙は全体が知っているが、建築資材や貿易については専門知識が必要になり、受注して配車係に指示する時、特に混載で積み合す場合は、詳しい荷姿や引取り状況や降ろし状況をコト細かく指示する必要があるからだ。
第35期経営計画発表会
経営計画発表会を恒例の伊香保温泉郷で行う。約30分を使って2013年の方針を社員に伝える。以下要約
運送会社の経営は年々厳しくなっている。同じ環境は町の酒屋と類似している。酒屋も規制緩和により、郊外型スーパーやコンビニ・ネット販売等次から次にライバルが出現している。酒屋問題は新業態に勝てるビジネスモデルがないこと。だから後継者が育たず、廃業が続く。
運送会社も物流二法により規制緩和が進み、運送業は参入障壁が低いので新規参入が後を絶たない。運送の仕事は多くの場合車輌さえ持てばお客様でも出来るが、運送会社に頼むのは、自社で運ぶより安いからである。中小運送会社の92%は赤字と言われている。問題点は酒屋と同じ様に黒字を確保できるビジネスモデルが少ないこと。
総合トラックにはそのビジネスモデルがある。物流コンサルタントの話に私なりに複数社の元気な運送会社を分析した結果、数パターンに集約されそうだ。当社は鋼材・小口という切り口でプラットホーム型のサービスを提供している。又150社の運送会社に協力いただきお客様の購買代理店型のモデルをもっている。
でもモデルがあるから仕事が順調に行くのではなく、どこまで徹底してその仕事を深堀するかである。
(写真: 経営計画書、手前の4冊はこの一年間に入社した社員)
「大した事ない」
事務所でクレームやトラブルらしき電話を耳にすることがある。「今の電話何なの?」と聞くと、状況説明の後に「大した事ありません」という言葉が付け加えられることがある。でも、過去を振り返りこの「大した事ない」に惑わされて初動が遅れて多くの犠牲を払ってきたし、お客様の不満を闇にもみ消してきたかもしれない。
この言葉の裏にはいくつかのケースが考えられる。
①大きいミスや大きな事故に比べて、大した事ではないとの判断
②上司に安心してもらうため、冷静に対応するための配慮、
③お客様はこちらからの対応や説明で一応納得してもらった
④自分のミスを社内のメンツから、もみ消そうとする時
「大した事ない」は何もしなくても大丈夫と捉えがちだし、「処理は私に任せて下さい。上司の出番ではない。」との意志表示ともとれる。過去の痛い経験もあるのでそれでも屈せず、軽く捉えるなとの意見や具体的な指示は出す。
自宅で絨毯にワインをこぼしたとする。そのもの音に隣の部屋にいる家内が異常に気づき「あなた何かあったの」と聞かれたら、反射神経として「大した事ない」と返事をする。その時にはいくつかの心理が働く。自分のミスを揉み消したい、怪我はしてない、クラスは壊してない等、でも絨毯は真っ赤。直後の惨状を家内に目撃されたたら、それこそ大事件である。直ぐさまタオルをもってきて掃除しはじめる。あらゆる手段を使ってそしてシミが最小限になった時に「ちょっとコボした」と白状する。
この程度なら笑えるが、会社単位の経済活動となると問題軽視や問題の先送りは重大問題となる。「大した事」や「大した事でない」はお客様が判断することなのだから、思い込みによる問題の程度の報告は要らない。