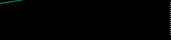だいちゃん Diary

供給過剰、それとも弱者
大阪のA社から聞いた話。100台を抱えるA社は長距離輸送部門もあり、40台のトラックが東京⇔大阪間を毎日運行している。今回の軽油の高騰は、値上がり分だけで年間2000万円以上のコストアップ要因になる。我慢に我慢の重ねたが、とうとう主要荷主に値上げ交渉することに。「値上げを言っきたのは貴社だけ、値上げは了解しても良いが、当然仕事が減ることは覚悟してほしい。」と言われたそうだ。結局仕事確保に値上げは撤回する。ではどこでそのコストアップを吸収していくのか。高速代・車両代金・保険・税金は定額、結局は赤字を出すか運転手の給料を下げるかの選択をせまられることになる。物流業は、参入障壁の低い業界だ。
リンボー車
今週から稼動を始めるリンボー車、荷物の量に応じて天井が上下する。写真は低い状態で、通常のアルミバン車に比べると何だか不格好な感じもする。天井の低い積込み場所では、効果的な車両だ。
洗車
担当が乗り変わりの為、大型車の洗車を行う。運転台から開始、車から取り出せるものは全て車外に出し、数種類の洗剤を使い分け、雑巾がけ。運転席周りのパネルは「つまようじ」と歯ブラシを使い汚れをかき出す。乗用車と違い大作りなので拭き易いが、拭いても拭いてもまだまだ拭く部分がある。運転台だけ二人で洗っても、二時間あっという間に経過。次は足回り。黒く塗装された足回り、腰をかがめながら洗車ブラシをすき間から差し込んで洗う。梅雨の最中でだいぶ泥が跳ね上がっており苦戦、月曜日が雨だとこの努力は全て無駄になるかなと余計なことも考える。一周まわると20メーター、足腰がふらつく。足回りはトラックを綺麗に見せるポイント、特にシャーシ部分が綺麗だと、上部が多少汚れていても綺麗に見える。キャビンは家庭用洗剤を使って、「どこか、かゆい所ないですか」と聞きながらシャンプー、ここまでくるとトラックも気持ち良さそうに見える。水で綺麗に流し、そして仕上げにワックス。 男前になりました。 フー。
(写真: コックピット内は収納部分が多く、快適な空間。)
ドライバーS君
ドライバーS君は俳優だったら間違いなく悪役、顔が怖く、無口。外見とは正反対に、気持ちはやさしく、自分を不利にしてもお客様や仲間を優先に考え行動する。S君の配達は、不思議と早い。例えば朝8時からに荷受するお客様でも、彼が数回行き始めると、6時にでも降ろしてもらえるようになる、こんなことが頻繁にあり兎に角不思議。道路の情報量も圧倒的に多く、渋滞日でも普段と同じ時間に帰ってくる正にプロ。当然、お客様からの評価は高い。ただ無口で自己主張しないので、「らしい」とか「不思議」としか説明できないのが残念。
トラックカラー
営業トラックのカラーリングは一般的には明るい色使いで、ラインが入っているケ-スも多い。わが社のカラーリングはグレー一色で、暗いイメージである。
総合トラックの前進は、私の父の経営していた(現在は兄)梶哲商店にある。海軍出身の父は、軍艦のグレーが気に入っており、トラックもその色にした。何度か明るい色への変更を願いでたが全く受け入れられなかった。
軍隊の規律が好きな父は、ヘルメットもグレーにして着用にもこだわった。現場でヘルメットを着用しない数人の運転手といつヘルメットをかぶるのかを議論したことがある。トラックを降りる時か、地面に足を付く瞬間か、作業に取り掛かる時か。どれも曖昧になりかけた時期、父の独断で就業時間中(運転中も含め)ヘルメットをかぶる事を全員に義務つけ、その規則は20年間続いた。
ヘルメットをかぶった顔しか見た事がないので、職場以外で会って誰かわからないことも度々あった。その規則は、総合トラック時代になってから廃止された。
父が指定した色は、トラック購入時にいつもと同じ色でと言うだけで大雑把な管理だったが、先日横須賀で軍艦三笠を見た際現在の弊社のカラーと全く同じで、ある意味ホッとした。
(写真2: 軍艦三笠)
ブランド
ブランド管理のしっかりしている企業は、物流の仕組みも取組み方も違う。
清涼飲料の自販機へ補充する仕事に携わる物流会社の方から聞いた話。
一般的に輸送途中に缶に凹みが出ると物損対象となり、物流会社が代金を補填する。そうすると運転手の心理で、ちょっとしたキズや凹みだったら判断が甘くなったり見過ごすこともある。
あるブランド力のある飲料メーカ-は、自販機への輸送途中の物損は一切責任は問わず、どんどん返品を受け付けるという。コインを入れ、出てきた飲料が完璧である仕組みが明確に差別化されている。
恥ずかしながら当社が一流ブランドのティッシュで水濡れを起こしたことがある。その時のメーカーの対応は敏速で、その選別作業に上席の方が現場で立ち会われ、湿気を帯びている可能性のある商品は全てコストをかけても自社で廃棄し、員数管理も厳密にされていた。ブランドへの熱い想いが伝わってきた。
社内研修
日曜日を利用して、経営計画書の理解を主目的とした社内研修を行う。
3ヶ所の事業所に分かれているので今回始めて会う社員もいる。4グループに分かれ課題を議論し発表していく。小宮コンサルの平井さんに講師になっていただき、緊張感のある研修になった。
嬉しい話
総合トラックの20年前からお取引のお客様から電話をいただき、小倉がお伺いして打合せさせていただく。その中で、弊社のホームページがメタル便にリンクされていることから、弊社がメタル便に関わっている事を知り驚いたと言う。
振り返ってみれば、メタル便サイドからは総合トラックのことは余り触れていないのでその関係は理解はされてないと思う。メタル便の機能を絡めてお話に展開していったようだ。
田中久夫先生
赤倉温泉で行われた、田中久夫先生の勉強会に参加する。
田中先生は、50歳(しかも物流には全くの素人で)過ぎてから倒産寸前の名糖運輸の社長を引き受け、見事再建され一部上場にまでにした方だ。現在も86歳の年齢で、経営コンサルタントとしてご活躍され、十数社の会社も定期的にご指導されている。
理屈ではない社長としての想いを多く語られていた。
(写真: 昨年出版された著書)
書店?それとも本屋?
知人から聞いた話。
「○○書房は本屋ではなく書店を目指し店舗展開している。地域性を分析し、教材か娯楽かビジネス書か、何が売れるか徹底した事前調査の上で出店している」と言う。
業界は異なるが、常日頃同じことを私も言っている。「運送屋ではなく、運送会社になりたい。」その意図するところは、個人に頼るのではなく、会社としてチームとして取組んでいきたいとの想いで。
ところが知人の話を聞きながら「本屋がなぜ悪い」と疑問をもった。本屋には売る人と買う人の交流が存在し、温かみを感じる。書店は科学的で緻密な経営がなされるかも知れないが、使用者にとってそれが全てではない気がする。
我々に運送の仕事を出していただいているお客様も「運送屋がなぜ悪い」と同様な意見を持たれているかもしれない。